
地域の発展を支えた今治港…人が賑わう交流拠点として未来へつなぐ
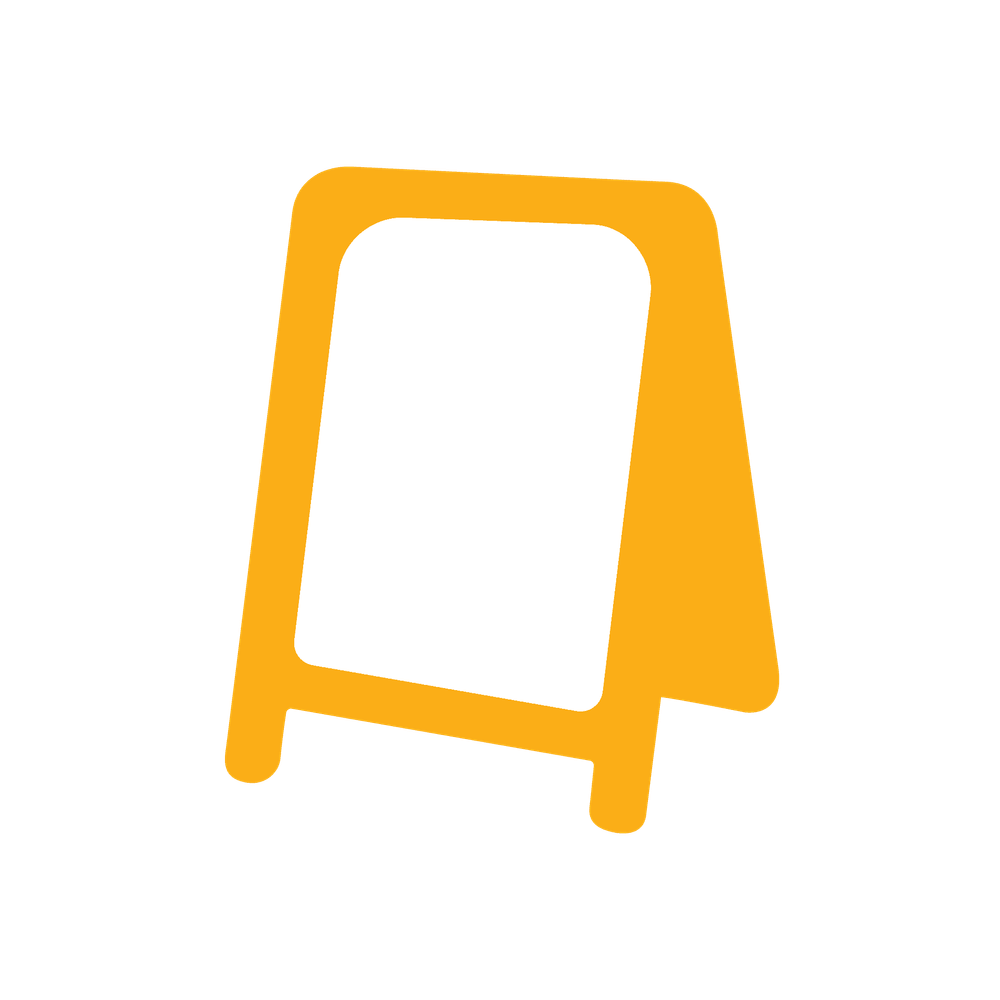
Streets magazine 編集部
2024年10月4日
瀬戸内の海上交通拠点として今治の発展を支えてきた今治港。しまなみ海道の開通とともに航路廃止が進んだものの、交流センター「はーばりー」の整備等で新たな交流拠点として生まれ変わっています。

今治港の歴史
今治港の始まりは今治城築城時に堀と海をつなぐ舟入船頭町を作ったことが始まりといわれます。明治に入り今治と大阪航路を開設したのが「海の恩人」とも呼ばれる飯忠七(いいちゅうしち)です。大型船の誘致で今治タオルのルーツでもある伊予綿ネルの発展を支え、1922年(大正11年)には四国初の開港場(外国との貿易が許された港)に指定されました。飯忠七の功績を称え、今治港の広場には今も碑が残されています。


島々の生活を支えた渡海船
今治港の昭和の懐かしい風景として伝わるのが「渡海船」です。今治港から瀬戸内の島に野菜や日用雑貨品などを運び、人の交通手段だけでなく島の経済を支える重要な役割を果たしていました。渡海船は島の各地区から出ていて、昭和30年代には約50隻あったといわれていますが、フェリーの就航が進み渡海船はその役割を終えました。

1970年頃の渡海船
しまなみ海道開通で今治港の役割変化
1960年代以降、今治港には広島、関西、瀬戸内の島々を結ぶフェリーが就航し、1974年には今治港の乗降客が290万人を超えるほどになりました。しかし1999年のしまなみ海道開通で交通の足が船から車へとシフトし、定期航路は徐々に縮小。観光港としての今治港は大きな変化の時を迎えました。

今治港は新たなにぎわいの交流拠点に
2015年、今治港に船の形をイメージした「みなと交流センター はーばりー」が整備され、開港から100年を迎えた2022年からは毎月第2、第4日曜(夏場は土曜夜)に「せとうちみなとマルシェ」がスタートしました。開催日には色とりどりのテントが港に並び、旬の野菜や新鮮な魚を求めて1万人近い人が集まります。かつて大型船やフェリーが行き交った今治港は今、人と人が交わる「にぎわいの港」として生まれ変わろうとしています。

